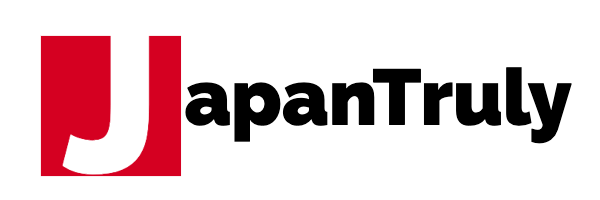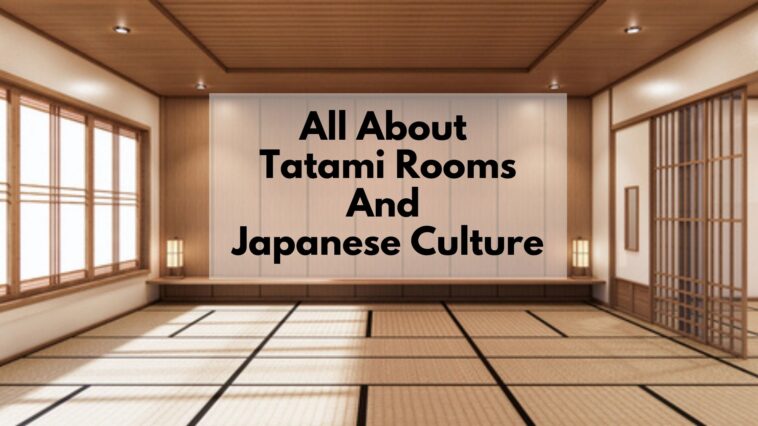伝統的に、日本の床は 畳の部屋 は稲藁で編んだ畳で覆われています。この分厚い畳は、人が床に座ったり寝たりするのに適しているからです。畳の歴史や用途、畳部屋の構成要素などをご紹介します。
畳の部屋は、単なる床マットの域を超え、伝統に彩られたユニークな空間を作り出します。歴史的なルーツから、日本建築に欠かせない風習やエチケットまで、日本家屋における畳の文化的意義をご紹介します。
タタミルームとは?
日本では昔も今も畳が広く使われています。
畳は、「たたむ」という言葉に由来します。畳は伝統的に、乾燥したイ草で織られ、稲藁の芯に縫い付けられていました。


これは、床の上での休息をより快適にするためのものである。作りたての畳は、美しい緑色をしており、稲藁の独特の匂いがする。
時間が経つと、緑はくすんだ黄色に変わり、香りも消えていきます。
サイズは3フィート×6フィートで、大人が使うのにちょうどいい大きさです。使用しないときは、折りたたんで積み重ねておきます。
畳は富裕層や貴族だけが持てる贅沢品で、庶民は硬い床で休むしかありませんでした。
その起源は、室町時代の14世紀にまで遡ると言われています。
その後、稲わらは合成素材に変わり、安価でお手入れも簡単になりました。
日本における畳文化の起源と歴史
畳は、平安時代(794-1185)から日本人の住まいに使われてきた、日本の伝統的なインテリアの代表的な要素です。
この伝統的な筵の作り方、敷き方は当時から受け継がれ、現代の日本の家屋の風景にもキラリと光っている。
畳は、12世紀ごろに、い草や柔らかい草を詰めた国産の材料で作られたのが始まりと言われています。当時の貴族たちが宴会や接待をする神聖な部屋に、このしなやかな畳を敷いていたのです。
時代とともに、下層階級の人々もこの貴重な座敷に入ることが許されるようになり、社会階層を超えた文化として定着していったのです。
この初期の畳は、日本古来の木の床を保護し、人々が優雅にくつろぎ、食事をするための快適で柔らかい空間を提供しました。
当初、畳は砕いた乾燥ヒノキと柔らかい草を、帯状の布を縫って束ねたもので、現在の畳の象徴であるクッション性を持たせている。
畳には、花や丘などを刺繍して装飾を施す人が多くいました。
漆塗りのトランクや洗面器、柄物の錦を使ったベストなど、畳は本来の床材としての役割を超えて、芸術の域に達したのです。これらのユニークな作品は「袱紗(ふくさ)」と呼ばれ、現在でもお座敷で見ることができる。
畳の縁にはローテーブルや座布団が置かれ、中央には床の間が置かれ、美術品や象徴的な花、季節の飾り物が置かれるのが一般的です。
何世紀もの間、畳は手作業で作られ、手間のかかる仕事と言われてきました。
畳は手作業で縫い合わされ、藺草も手作業で結ばれていた。手づくりの材料は高価なため、畳の部屋は富裕層や貴族しか利用できなかった。
現在、畳は工場で生産され、い草の代わりに発泡スチロールやトウモロコシの皮などの代替材料が使われています。
マットはミシン縫い、部屋は現在一般的なものです
しかし、日本の文化や歴史の中で尊敬される存在であることに変わりはありません。
畳はなぜ高いのですか?
畳を織るのは手間のかかる作業です。機械で簡単に作れるようなものではありません。日本には、畳を織るための特別な訓練を受けたアーティストがいます。

この合成繊維や稲わらの芯が、このマットの特徴であるバネ性を生み出し、しっかりとした座り心地や寝心地を実現しています。
タタミルームの目的
畳の部屋とは、皆さんが想像している通り、畳がある部屋のことです。
畳は日本の貴族の休息の場として使われていました。現在の畳の部屋は、マットだけではありません。
畳の部屋は、クッションや布団を入れるとさらに快適になります。ただし、あまり重い家具を置くと、畳が傷んでしまいます。
また、畳の部屋は天井が低く、ライスペーパーブラインドがあることが多い。畳はあまり丈夫ではないので、あまり踏まない場所に使われます。
共有スペースに畳が使われている場合は、靴を履かずに踏むのがベストです。
最近では、お寺の勉強部屋としても使われています。家庭では、畳はあらゆる用途に使われています。リビングや休憩室として使う人もいれば、赤ちゃんや子供の遊び場として使う人もいます。
畳の部屋の要素
日本では、部屋の大きさを畳の数で測る人が多い。
畳は、家の茶の間や休息したい部屋にごく普通に使われています。
日本の文化では、バランスと調和をとるために、部屋ごとに特定の数字を使うことがあります。
畳はデリケートなので、部屋に置く家具にも気を配らなければなりません。
共通する要素がいくつかありますので、以下にご紹介します。畳は折りたたんだり、重ねたりするだけなので、汎用性が高く便利です。
畳は、スペースに余裕のあるモダンでコンパクトな住宅にとてもよく合います。
スライディングドア。襖(ふすま
畳の部屋には「襖」と呼ばれる引き戸があります。襖は本来、絵描きのための厚いキャンバスでしたが、いつしか部屋の間仕切りとして使われるようになりました。

厚みのある不透明なシートを木枠で支え、スライドさせることで空間を開放的にしたり、閉じたりすることができます。
この襖は、寺や神社では凝った装飾や絵が見られます。一般の家庭では、もっとシンプルで無地のものが多いです。
The Partitionsです。Shouji
障子とは、木の格子で支えられた半透明の仕切りのことです。これも襖と同じような用途で使われます。
襖と障子の違いは、障子の方が透光性が高いため、部屋の外に置いて光を取り入れるのに対し、襖は家の中で使うということです。
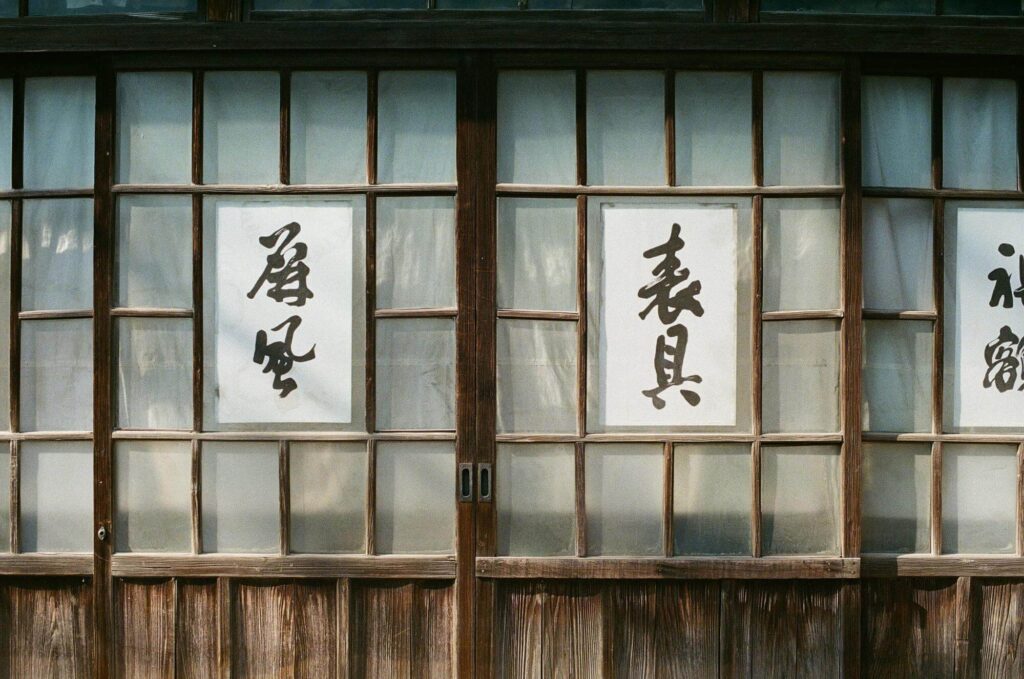
半透明なので、プライバシーを確保しつつ、自然光を遮断することができます。最近のShoujiでは、片面がガラスになっていることもありますが、以前は空気も入ってきました。
ザ・クローゼットオシレ
オシイレは、収納のためのビルトインクローゼットです。最近のコンパクトな家では、これがとても便利です。
畳の部屋で使う余分な布団やリネン、クッションなどを入れておく人が多いです。
また、部屋の掃除をするときには、畳を収納しておくとよいでしょう。
畳の部屋には、「千木棚」と呼ばれる棚が設置されていることがあります。これは、花瓶やお香などの装飾品を置くためのものです。
ローテーブル。こたつ
畳の部屋では重い家具は使えませんが(畳を長持ちさせたい場合)、多くの日本人は「こたつ」と呼ばれるローテーブルを使っています。
日本には食事などで床に座る習慣がありますが、その時に使うのが「こたつ」です。
特に冬場のテーブルは、下から熱を入れて暖かくし、毛布をかけます。
布団とクッション(ざぶとん)
布団は、畳の上に直接置くことができるプレーンなマットレスです。
畳の上で休んだり寝たりするためのものです。日本の家庭では、多くの畳の部屋に布団が敷かれています。
使わないときは、畳んだり丸めたりして、作り付けのクローゼットの中に入れておきます。畳の部屋では、より快適に過ごすために座布団を使うこともあります。
肘をついたり、膝をついたりするときに使います。このクッションも使わないときは押入れに収納されています。
畳の部屋の利用。
畳の自然素材とその織り方は、部屋の温度を調整するのに役立ちます。
畳を部屋の壁一面に敷き詰めると、断熱効果が得られます。
寒さを防ぎ、熱を逃がさないので、厳しい寒さの冬でも部屋の中の人を暖かく快適に保つことができます。
夏になると、この畳が暑さを防ぎ、室内を涼しくしてくれます。また、部屋の空気を新鮮でさわやかに保ちます。
腰痛に悩んでいる人は、痛みを和らげるために畳や畳の部屋が最適です。

畳は、弾力性がありながらもしっかりとしていて、足や腰をしっかりと支えてくれます。裸足で歩いたり、薄い布団を敷いたり敷かなかったりするのに適しています。
また、その上でヨガをする場合にも、しっかりとサポートしてくれます。
畳のお手入れ方法
畳の掃除は、日本の伝統的な床を最高の状態に保ち、時間の経過とともに蓄積される汚れ、ほこり、アレルゲンを除去するために不可欠です。
定期的なメンテナンスとクリーニングで、畳は何十年も保つことができ、どんな部屋にも美しい、時代を超えた外観を提供します。畳は繊細に見えますが、正しい道具と説明書があれば、驚くほど簡単に掃除ができます。
まず、柔らかいブラシアタッチメントで畳に掃除機をかけます。そうすることで、溜まった大きなホコリやゴミを取り除くことができます。
その後、手持ちの掃除機か布張り用アタッチメント付きの掃除機で、もう一度マットの上を掃除して、小さなゴミやアレルゲンを取り除きます。
汚れがひどい畳は、この作業を何度か繰り返して、できるだけきれいにするとよいでしょう。
次に、湿らせた布で畳をやさしく拭きます。水分が多すぎると畳をダメにしてしまうので、水滴が付かない程度の湿った布を使うことが大切です。
水滴がなくなるまで完全に絞ってからマットを拭いてください。
マットの上部から下に向かって、汚れやほこりを落とすと、すでに濡れている表面に降りかからないようにします。
汚れがひどいところは、布に少し洗剤をつけるか、畳専用のクリーナーを使うとよいでしょう。
マットがきれいになったら、乾いた布で残った水分を拭き取ります。マットを完全に乾燥させてから、続けてください。
畳の大きさや厚さにもよりますが、数時間かかることもあります。この間、畳を振ったり、回転させたりして、空気を抜くとよいでしょう。
最後に、窓を開けたり、扇風機を使ったりして、空気を循環させ、乾燥を早めましょう。
適切な道具と説明書があれば、畳の掃除は簡単です。定期的なメンテナンスとクリーニングは、畳を長持ちさせ、どんな部屋にも時代を超えた美しい外観を与えるために不可欠です。
畳の掃除の仕方を知って、これから先も畳を持つ喜びを味わってください。
畳の衰退。
最近では、畳の売り上げが大幅に減少し、多くのアーティストがすぐに廃業してしまうのではないかと危惧しています。
今でも畳が好きな人は、安い材料で大量生産され、中国から輸入された合成繊維の畳を買っています。
本来の畳に似ているのは見た目だけで、食感や健康増進に役立つものではありません。
稲わらで作られたオリジナルの畳は、手入れがとても大変です。
畳の部屋で重い家具を使うと、畳に傷がついてしまいます。多くの人が畳を長持ちさせるために裏返して使用しますが、それでも数年しか持ちません。
また、畳は水に濡らさないようにしなければなりません。水に濡らすと藁がダメになってしまうからです。忙しい生活を送っている人にとっては、メンテナンスはとても大変です。
世界では東洋の要素を取り入れようとしていますが、日本のモダンな家は西洋の要素を取り入れようとしています。
日本には洋風の家具がたくさん輸入されています。
伝統的に日本人は床に座り、薄い布団で寝ていましたが、今ではダイニングテーブルやカウチ、勉強机、重いコットなどが求められています。
これらは畳にとって有害であるため、人々やデザイナーはより持続可能な床材を探そうとしています。
また、生の畳の色や匂いを不快に感じる若者も少なくありません。
また、緑からくすんだ黄色に退色することで、インテリアの美しさが損なわれると感じています。
これも、現代の日本人にとって畳が古臭いと言われる理由の一つです。
また、読んでください。