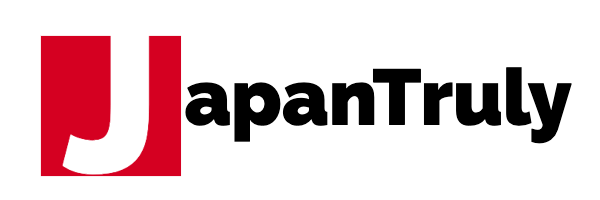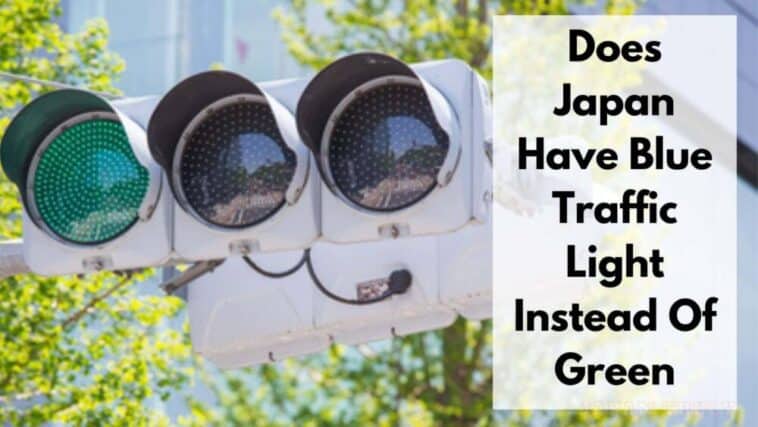日本には青信号があるのか?詳しくはこちらをご覧ください。
なぜ日本は信号が青いと言われるのか?その理由を探る!言語と文化的規範がどのように組み合わさって、日本独特の信号機体験を作り出しているのかを学びましょう。
なぜ日本では信号が緑ではなく青なのか?
日本の信号機が青く見えるのは、言葉の癖によるものだ。青」という言葉は伝統的に青と緑の両方を意味していた。現在では緑を表す「ミドリ」があるが、「GO」信号の正式名称は依然として「アオ」である。厳密には緑色だが、非常に青い色合いである!
文化は人それぞれ。言葉にはさまざまな意味があり、そこには個人の信念も大きく関わってきます。日本の信号機の色には、まったく別の裏話があり、興味深い指摘があります。

日本人の色の好みが緑から青にシフトしていますが、これは設定の不具合や色落ちのせいではなく、別の要因があるのです。次の項では、それについてさらに詳しく解説します。

信号機というのは、すべて日本語と関係がある。昔、青と緑という色を同じ言葉を使って表現していたことに起因する。
当時は、黒、白、赤、青の4原色しかなかったので、緑色のものは青色で表現していたのです。この習慣は何百年も続きました。
千年紀の終わり頃、人々は緑を色ではなく、「ミドリ」と呼ぶようになった。本来の意味は「新芽」だが、「アオ」の色合いとして理解されるようになった。意外に思われるかもしれませんが、この使い方は現代でもごく普通に使われています。
日本でリンゴが食べたくなったら、近くの八百屋に行けばいい。店員さんに「リンゴをください」と言うと、「ミドリ」ではなく「アオ」と言われるはずです。
青信号のことを「アオ」と呼ぶのは、現地で話されている言葉だけでなく、公式文書でも使われている。
1930年代に日本で初めて設置された信号機は緑色だったにもかかわらず、「青色」と表記され、日本政府は言語学者との間で問題になった。
国際法を遵守するために、公式の表記ではなく、ライトの表記を変えることにしたのだ。
1973年、政府の命令で信号機の色は、できるだけ青に近い緑色でなければならないことになった。
現代でも、自動車運転免許の試験に合格するためには、赤・黄・青の区別がつくことを証明しなければならない。
赤・黄・緑の3色は、74カ国が批准している信号機の色に関する国際条約で決められている。しかし、日本はこの条約に加盟していません。
日本の7種類の信号機
青信号が使われる理由がわかったところで、今度はさまざまな種類の交通が存在することを啓発する。
日本のドライバーは、日本の交通規則を遵守することが不可欠です。信号機は、場所や交通量、交差点などの条件に合わせて、さまざまな種類が設置され、よりスムーズに通行できるようになっています。
#1 - 押ボタンタイプ。
信号機の制御には、押しボタンが使われます。歩行者が道路を横断できるように、押すと赤信号を青信号に変えるボタンがあります。
#2 - スタッガード信号
一方向のみ青信号の時間を長くすることで、渋滞を緩和するための信号機です。右折車がかなり多い道路に設置された。
#3 - センシティブタイプ
この信号機の特徴は、検知器があることです。この信号機は、道路そのものに設置する場合と、交差点の入り口に設置する場合があります。ただし、道路を横断する車両や歩行者がいるときだけ信号が青になります。
#4 - 固定サイクル式
交通信号機の一種で、通過する車両や歩行者の流れをよりよく整理するために、青・黄・赤の3色の信号を所定の間隔で交互に点灯させるものです。
そのほかの種類としては、タイムスイッチを使って交通量の多い時間帯や曜日を判断し、信号の表示を変えることができる「マルチステージ・システム」がある。これは、多段式にすることで実現しています。

#5 - アロータイプ
矢印信号は、その位置的に3色信号機の真下にあります。3色信号で赤信号が点灯しても、車両は青矢印の方向へ進むことができます。
この矢印信号には、「右方向を指す矢印」と「矢印を分離して表示する」という2つのバリエーションがあります。
#6 - 歩行者用車輌分離型
道路を横断する歩行者を車両から物理的に分離し、安全を確保するために設けられた特定の種類の交通信号機。車両用の信号機が赤一色の位置にあるとき、歩行者用の信号機は青に変わる。
歩行者の斜め横断を許さない「歩行者専用表示」と、歩行者の斜め横断を可能にする「スクランブル」の2つの方式を採用しています。
#7 - 歩行者支援情報システム
目の不自由な方の安全を確保しつつ、横断歩道を渡りやすくするための方法です。
なぜ日本には青い信号機があるのか?
日本の信号機は、赤、黄、緑という伝統的な色に加えて、青の「GO」ランプを備えている。しかし、これは配線とは関係なく、完全に日本語に関係する問題である。昔は、青と緑を同じ言葉で表現していたのだ。
日本人はなぜ緑のものを青と呼ぶのか?
みどりは、1930年以前は緑を表す言葉であった。一方、日比谷に初めて信号機が設置されたのは1930年3月で、その時にマスコミ(当時の新聞を指す)が初めて「アオ」という言葉を使ったという。青と言われた方が、多くの人が喜ぶと考えたからだそうだ。
日本に緑色の光はあるのか?
1973年、政府は信号機にはできるだけ青みを帯びた緑色を使用するよう政令を発した。これは、「青」の名称を使い続けることを正当化するためであった。
結論
日本には青い信号機がありますが、これは配線の不具合などとは関係ありません。その判断には根拠がある。今、述べられたように、言葉の使い方と何らかの関係があるのである。
その理由がわかったところで、日本にいるときは気をつけたいものです。色について学ぶだけでなく、日本の交通ルールをよく理解した上で運転するようにしましょう。
運転免許を取り消される危険もあります。最後に、運転中はシートベルトやヘルメットを着用することを忘れないでください。日本の信号の仕組みもしっかり覚えておきましょう。それでは、よいお年を
関連記事